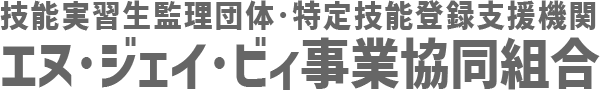なぜ宿泊業が技能実習の職種・作業に追加されたのか?
近年、東南アジア諸国は急速に発展しており、ホテルやその他の宿泊施設の開発が進んでいます。
この経済発展に伴い、所得の増加と旅行需要の高まりが見られます。
このような背景のもと、日本のホテルや旅館などの宿泊業において技能実習を行い、技能や知識を学び、自国の宿泊業の発展に役立てたいという需要が高まっています。
2020年2月25日からは、宿泊業が国人技能実習法に基づく技能実習制度の「技能実習2号」の移行対象職種に追加され、宿泊業での技能実習生の受け入れが可能になりました。
これにより宿泊業界における国際的なスキルの向上と発展を促進することが期待されています。

宿泊業における技能実習生の作業の内容が定められています
宿泊業における技能実習生の作業内容は、宿泊、飲食、会合等での施設の利用客に対する到着時・出発時の送迎、チェックイン・チェックアウト作業、滞在中の接客作業や料飲提供作業、またそれらに伴う施設の準備・整備、利用客の安全確保、衛生管理のための作業を技能実習で行います。
技能実習1号と技能実習2号では技能実習中に行うことが出来る必須業務内容は異なり、下記のとおり定められていることに注意が必要です。
必須業務とは、この職種や作業で定められた業務であり、全て実行する必要があります。
記載された業務は、但し書きがない限り、一つも省略せずに行う必要があります。
| 第1号技能実習 |
|---|
| 接客・衛生管理作業 ⑴利用客の送迎作業補助 ①到着時、出発時の送迎 ②手伝いを必要とする利用客への対応 ⑵滞在中の接客作業補助 ①利用客への挨拶 ②客室への注文品の配送・提供 ③荷物の預かりと返却 ⑶会場準備・整備作業補助 ①会場の清掃と準備 ②テーブルセッティング ③食器類の後片付け ⑷料飲提供作業補助 ①注文の受付(アレルギーの確認を含む※5) ※5アレルギーの有無を上司に確認 ②料理の提供(手消毒を含む) ③飲物の提供(手消毒を含む) ⑸利用客の安全確保と衛生管理補助 ①利用客の安全確保 ②衛生管理 |
| 第2号技能実習 |
|---|
| 接客・衛生管理作業 ⑴利用客の送迎作業 ①到着時、出発時の送迎 ②手伝いを必要とする利用客への対応 ⑵チェックイン・チェックアウト作業補助 ①チェックイン ②チェックアウト ⑶滞在中の接客作業 ①利用客への挨拶 ②客室への注文品の配送・提供 ③荷物の預かりと返却 ④館内・周辺施設の案内 ⑷会場準備・整備作業 ①会場の清掃と準備 ②テーブルセッティング ③食器類の後片付け ⑸料飲提供作業 ①注文の受付(アレルギーの確認を含む※6) ※6アレルギーの有無を利用客に確認し、その有無を上司に報告 ②料理の提供(手消毒を含む) ③飲物の提供(手消毒を含む) ④精算 ⑹利用客の安全確保と衛生管理 ①利用客の安全確保 ②衛生管理 |
技能実習生の受入れが可能な宿泊施設
ホテルや旅館などの宿泊業界が技能実習生の受け入れ対象職種として新たに追加されたものの、すべての宿泊施設が技能実習生を受け入れられるわけではありません。
宿泊業で技能実習生を受け入れるためには、以下の2つの要件が必要です。
- 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊施設
- 食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
許可を得ていない宿泊施設では技能実習生を受入れることが出来ないことに注意が必要になります。
技能実習生の要件
技能実習生を受け入れる際には、誰でもが対象となるわけではありません。
具体的な要件の一つとして、技能実習生は日本で行う予定の職種について、出身国でも経験を持っている必要があります。
たとえば、出身国で自動車整備の仕事に従事していた実習生は、日本で宿泊業の技能実習を行うことが認められていません。
技能実習生の受入れにはこのような要件が定められています。
技能実習生が次のいずれにも該当する者であること。
- 18歳以上であること。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事
- 業所から転勤し、又は出向する者であること。
- 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
- 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
技能実習を行う場合の実習実施者の主な要件
技能実習計画の認定
技能実習計画の認定は、法第9条(技能実習計画の認定基準)及びその関係規則に定められています。
- 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること
- 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること
- 同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと
- 第二号技能実習及び第三号技能実習にあっては、別表第二に掲げる職種及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)に係るものであること
技能実習責任者の選任
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
- 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を 監督することができる立場にある者
- 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機 関が実施する講習)を修了した者
技能実習指導員の選任
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
- 修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者
生活指導員の選任
- 生活指導員は、技能実習生の生活の指導を担当するために、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
宿泊業で技能実習生を受入れることのメリット
東南アジア諸国から青壮年労働者を技能実習生として受入れることで、日本の宿泊業で専門的な技能を身につける機会を提供します。
受入れの機会は、技能実習制度の目的でもある「国際貢献」や「人づくり」にもつながりますし、この経験を基に、彼らが後に「特定技能」の在留資格を取得して再び日本に来日し、就労する際には、既に習得した技術と経験を活かして、宿泊業界においてより長期的で安定したキャリアを築くことが可能となることが期待されます。