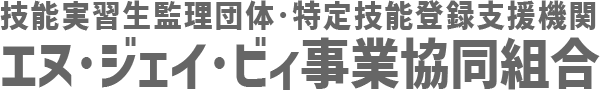建設業で外国人技能実習生の受入れをお調べの際、受入れの際にはどのようなことが必要なのか気になることがあると思います。
技能実習生を受入れるには、まず一般的な受入れ方法からご案内するところなのですが、このページでは建設業での技能実習生の受入れについて説明していきます。
ここでは建設業で受入れが可能な職種や作業から、受入れの際に満たすことが必要な要件、スムーズな配属につなげるための特別教育や技能講習についても説明していきますので、受入れご検討の際の一助となれば幸いです。

建設業における技能実習生の受入れのご案内
建設業界では、外国人技能実習生の受け入れに際して、通常の基準に加えて業界独自の要件が設けられています。
これは、建設業界の特性を考慮して、適切な労働環境を確保するために必要な措置です。
建設業では、作業場所が従事することとなる工事ごとに異なるため、個々の現場での就労の監理が求められます。
また、季節や工事の状況に応じて仕事の量が変動することがあり、それに伴い報酬も変動します。
これらの実情を踏まえて、技能実習生に適切な就労環境を提供するために、より厳格な基準が設けられています。

建設業における技能実習生の職種・作業
| 職種 | 作業 |
| さく井 | パーカッション式さく井工事作業 |
| ロータリー式さく井工事作業 | |
| 建築板金 | ダクト板金作業 |
| 内外装板金作業 | |
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 |
| 建具製作 | 木製建具手加工作業 |
| 建築大工 | 大工工事作業 |
| 型枠施工 | 型枠工事作業 |
| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
| とび | とび作業 |
| 石材施工 | 石材加工作業 |
| 石張り作業 |
| 職種 | 作業 |
| タイル張り | タイル張り作業 |
| かわらぶき | かわらぶき作業 |
| 左官 | 左官作業 |
| 配管 | 建築配管作業 |
| プラント配管作業 | |
| 熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 |
| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 |
| カーペット系床仕上げ工事作業 | |
| 鋼製下地工事作業 | |
| ボード仕上げ工事作業 | |
| カーテン工事作業 | |
| サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |
| 防水施工 | シーリング防水工事作業 |
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
| ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 |
| 表装 | 壁装作業 |
| 建設機械施工 | 押土・整地作業 |
| 積込み作業 | |
| 掘削作業 | |
| 締固め作業 | |
| 築炉 | 築炉作業 |
- 建設関係職種おいては建設関係(22職種33作業)が技能実習2号移行対象職種として定められています。
- 背景が赤の職種・作業は必須作業において特別教育や技能講習の受講が必要な職種・作業です。
- 背景が赤の職種・作業以外でも関連業務や周辺業務において特別教育や技能講習の受講が必要な場合があります。
建設業における技能実習生の受入れの要件
建設分野の技能実習計画の認定に当たり、外国人技能実習機構において審査することとされている基準は次のとおりです。
申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
建設業を開業する場合、軽微な建設工事以外は、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受ける必要があります。建設業の許可は、28の業種ごとに取得され、各業種ごとに営業するために必要です。
同時に複数の業種の許可を取得することも可能であり、既存の許可業種に業種を追加することもできます。一つの業種の許可を取得していても、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可を取得していない限り禁止されています。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
申請者、技能実習生が建設キャリアアップシステムに登録していること
建設キャリアアップシステムは、建設業界において従業員の能力や技能の向上、キャリアの発展を支援するための仕組みやプログラムのことを指します。
このシステムは、従業員が業界内での職種や技能の習得、向上を促進し、自己成長やキャリアの進展を可能にすることを目的としています。
※技能実習1号の実習生は、日本に在留していない段階ではキャリアアップシステムに登録することが出来ません。したがって日本入国後、技能実習2号移行時までにキャリアアップシステムへの登録が完了していることが必要です。
建設業の技能実習生の待遇の基準が月給制であること
建設業の技能実習生の待遇の基準として「技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと」とされていますが、具体的には技能実習生に対して、支払いが月給として毎月確実に支払うことが求められています。
技能実習生が日給制や時給制で働く場合、天候不良などで作業ができない日が続くと収入が不安定になることがあります。そこで、月給として安定した収入を保証することで、技能実習生が安心して技能実習に取り組める環境が整います。
技能実習生の人数が常勤職員総数を超えないこと
建設業の技能実習生の受入れ人数枠は独自に定められています。
具体的には「技能実習生の人数が常勤職員総数を上回らないこと」とされています。
常勤職員総数が7人の企業の場合、毎年3人の技能実習生を受入れる場合、1年目3人(技能実習1号:3人)、2年目6人(技能実習1号:3人、技能実習2号3人)、3年目9人(技能実習1号:3人、技能実習2号6人)となりますが、建設業の場合、常勤職員総数が7人ですので、9人の技能実習生を受入れることが出来ません。
受入れる際には技能実習生の人数が7人を超えないように調整することが必要になります。
※常勤職員総数には技能実習生の人数は含みません
特別教育や技能講習の受講が必要な場合があります
建設関係の職種においては、技能実習計画で定められた作業を安全に実施するために必要な特別教育や技能講習が義務付けられている場合が有ります。これらの教育や講習を受けずに関連作業を行った場合、罰則が科されることがあります。
特別教育や技能講習は、指定された施設でのみ受講可能で、数日から数週間の時間が必要となることがあります。また、通訳の手配が必要になることもありますので、受講計画は事前にしっかりと立てる必要があります。
組合では、これらの特別教育や技能講習の受講を支援しております。建設関連の職種で技能実習生の受け入れを検討中の企業様や、教育・講習に関してお悩みがある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
建設関連の技能実習生受入れサポート
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合では建設関連職種で技能実習をお考えの企業様のサポートを行っております。
建設業における技能実習生の受入れご検討の場合お気軽にお問い合わせください
当組合では建設業で豊富な受入れ実績がございます。
技能実習生受入れをご検討中で、下記のような場合お気軽にお問い合わせください。
- 建設業での受入れの場合について詳しく知りたい
- 自社がどのような職種や作業に該当するのか知りたい
- 実際に受入れる場合の費用やスケジュールについて詳しく知りたい
- 配属前の特別教育や技能講習の受講が可能なのか知りたい
- 技能実習生受入から特定技能で受入れるまでの流れについて説明して欲しい
- 送出し国や送出し機関、監理団体の変更を検討している